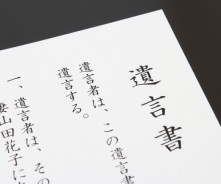
①自筆証書遺言である遺言書の保管者、②遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。自筆証書遺言の検認とは、相続人に対し遺言の存在を知らせ、遺言書の内容を明確にして偽造変造を防止するための手続きです。自筆証書遺言の検認申立費用や自筆証書遺言の検認手続きの必要書類をご案内します。
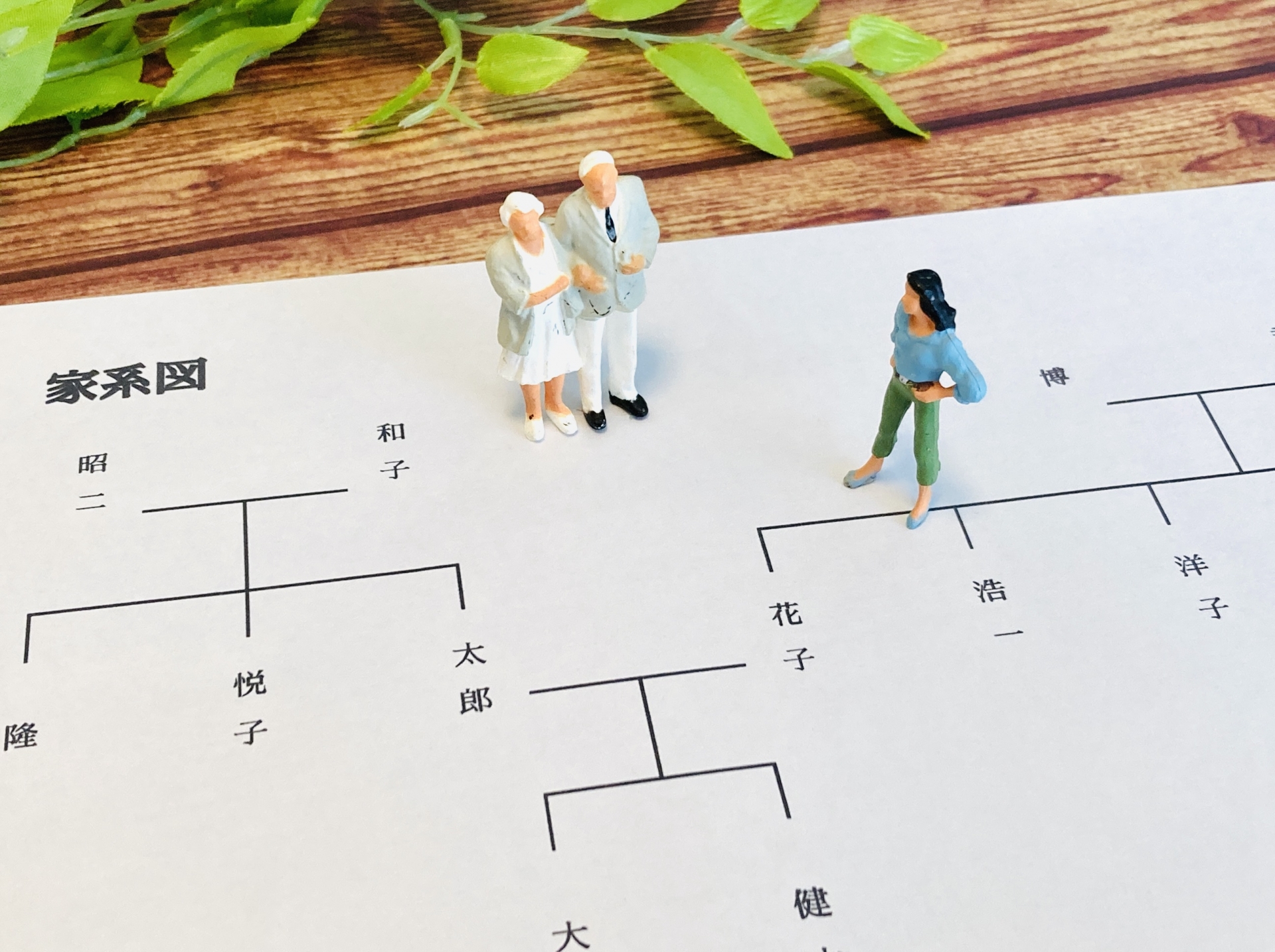
2018年7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、2019年1月13日から段階的に実施されています。
⑴遺産分割前の預貯金払戻が可能に
今までは遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では預貯金債権の払戻しができませんでした。令和元年7月1日付の改正で、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。(令和元年7月1日施行)

遺言とは、表意者の死後にその効果の発生を認める、一定の方式をもってなされた意思表示をいいます。遺言は必ず文書にしなければなりません。遺言書の作成方法には民法による決められた方式があり、それに従って作成しないと、法的に無効になってしまいます。遺言に書くべき内容、種類、取り消しや撤回、遺言書の保管と死後の扱いについて解説します。

①認知症、②寝たきり、③知的障害、④精神的疾病等で判断能力が不十分な人の財産管理(不動産の処分や預貯金の管理、遺産分割等の相続手続き)や身上監護(病院や施設入所の手続き)が必要な場合の成年後見申立は、当事務所にお任せください。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な人が安心して生活を送れるように本人の財産や権利を保護し生活を支援する制度です。